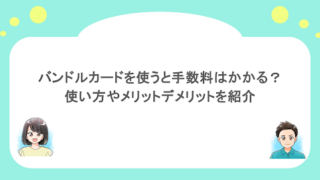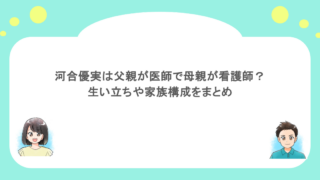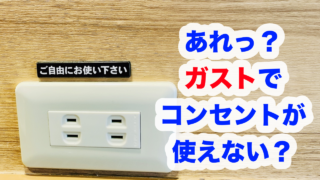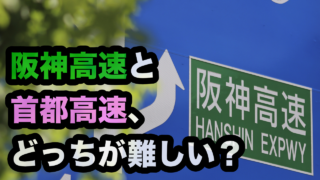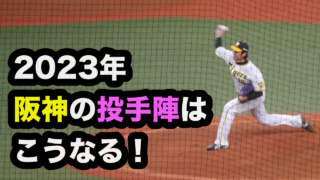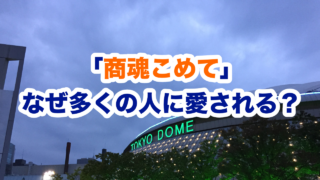関西人しか読めない文章とは?早口言葉もある?理由や発音のコツも伝授
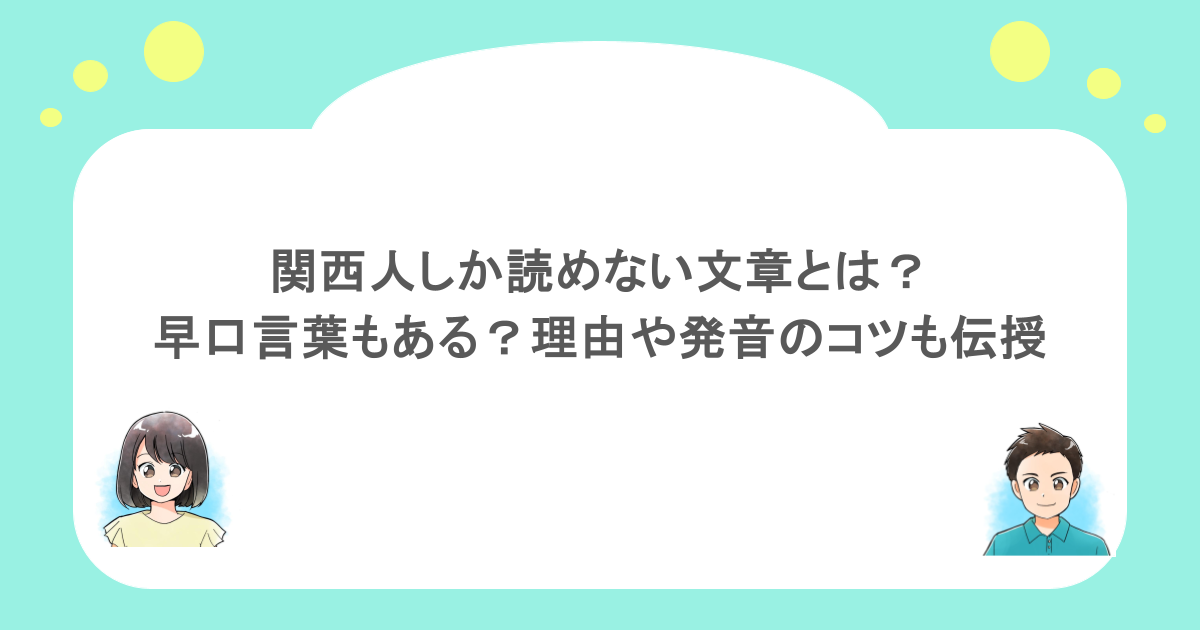
目次
日本では、同じ国であるにもかかわらず、いわゆる「方言」の影響で一部の地域の人の言葉が別の地域の人には分からない、なんてこともあったりしますよね。中には外国の言葉の方が一部の方言を習得するよりも簡単なんて言われたりもしますよね。
今回は関西人しか読めない文章や早口言葉、読み方のコツなどについて紹介します。
関西弁とは
関西人しか読めない文章が発生する理由は、やはり関西弁にあります。関西弁とは近畿地方、とりわけ大阪や京都などで話される方言で、方言の中では特別、他の地方で通じない言葉が用いられることは少ないですが、一方で「イントネーションが独特」という特徴があります。
かつて、日本の都は京都にあり、長く文化の中心地が関西にあったということで、昔のアクセントが根強く残っており言葉の変化も少なかったのだとか。関西の外では時の流れによって言葉のアクセントなども変わっていき、結果的に今では関西の言葉遣いが独特な物になっているのですね。
関西弁と標準語ではイントネーションが逆に!?
同じ言葉であっても関西弁と標準語ではイントネーションが異なる、という言葉はとても多くあります。その中でも、なんと「はし」についてはイントネーションが真逆になってしまうというのです!
「はし」というたった2音からなる言葉は「橋」「箸」と、同じ音で2つの意味を持ちます。口頭ではイントネーションで使い分けることができるのですが、標準語では「し」にアクセントを置くと「橋」、「は」にアクセントを置くと「箸」なところ、関西弁では「し」にアクセントを置くと「箸」、「は」にアクセントを置くと「橋」、真逆になってしまうのですね!
あくまで原典のお話
ただ、標準語を話す方や関西弁を話す方にとってもこの解説がしっくりこない、という人もいるかもしれませんね。現在は関東、関西での人の行き来も盛んですし、メディアなどの発達でそれぞれの言葉に触れる機会も多いです。混ざりあって曖昧になっているところもあると言えるでしょう。勿論文脈で判断できることも多いですし、箸の場合は「お箸」と、前に「お」をつけて話したりすることで区別するのが主流になっているような気もします。
関西人にしか通じない表現?
一見関西以外の人にも読めてるようで、意味は正しく通じていないという文章もあります。ここからは関西人にしか通じないかもしれない、関西特有の表現を紹介します。
「そのノートなおしといて~」
例えば職場で、デスクの上のノートを片付けてもらおうと、同僚に「そのノートなおしといて~」なんて言った場合、相手が関西人でなければそのノートの中身に記されている内容で、間違っている所を修正する、「なおす」ことを試みるかもしれません。「なおすところなかったよ?」と言われるかもしれませんね。
「なおす」が「片付ける、しまう」という意味で使われるのは、基本的に関西だけです。ただこの話も有名になりすぎて、関西でなくても意図を察してくれる人はいるかもしれませんね。
「このゴミほかしといて~」
「このゴミほかしといて~」といった感じで、「ほかす」という言葉を使うのも関西だけ。意味は「捨てる」、「放下す(ほうかす)」が語源ではないかと言われています。
「ゴミ」と一緒に使った場合はニュアンスを分かってもらえるかもしれませんが、使用済みのボールペンなどを指して「これほかしといて~」と言った場合、「え、どうするの?」となってしまうかもしれませんね。「ほかす」に関しては、なおすとは逆に最近は関西でもあまり使われていないような気もします。
「えらいこっちゃな~!」
関西では「それはえらいこっちゃな~!」「えらいこっちゃえらいこっちゃ!」と言った言葉を耳にすることもあるかもしれません。具体的な意味は分からないという人も多いかもしれませんね。「えらいこっちゃ」は「大変なことだ」といった意味の言葉です。「えらい」は「偉い」なので、立派、凄いといった意味で使われると思いますが、関西では「えらい」を「大変な」といった感じで使うのですね。
ですがそもそも関西弁では物事を大げさに表現する特性があるので、他の人からすると「そんなに大変なこと?」と思うようなことでも「えらいこっちゃ」と気楽に言ってしまう人も多いでしょうね。
関西人しか読めない早口言葉も!
関西人しか読めない早口言葉もあります。関西弁の特性を活かした早口言葉ですね。関西人以外だとうまく読めなかったり、そもそも文章として成立してないと思うかもしれませんね。
「チャウチャウちゃうんちゃう?」
関西弁の早口言葉の定番とも言えるのが、「チャウチャウちゃうんちゃう?」ですね。犬種の名前である「チャウチャウ」を用いた早口言葉で、「(あの犬は)チャウチャウじゃないのでは?」という意味の文章を、関西弁で言うと「チャウチャウちゃうんちゃう?」になるというわけです。
この早口言葉を読む時の発音のコツは、4つの「ちゃ」の音に意識を強く置くことです。「ちゃ」と発音した後に「う」はついてくるというイメージで、「ちゃ」をリズムよく発音するイメージでいけばうまく読めますよ。
「おっとっととっとってくれへん?」
続いて紹介するのは、お菓子の「おっとっと」を使った早口言葉です。例えば「おっとっとを残しておいて」という意味合いの早口言葉なら「おっとっととっとってくれへん?」となります。「と」が連続して続く早口言葉で「すもももももももものうち」みたいですね。「と」が連続で続くところが難しいです。「おっとっと」の最後の「と」と「とっとって」の最初の「と」を、違うアクセントで発音するのがうまく読むコツです。
関西人だけイントネーションが固定される文章も?
関西弁は基本歴史の流れを汲んだイントネーションなわけですが、比較的最近関西に根付いた関西独特なイントネーションもあります。
皆さんは「関西電気保安協会」という文字をどのように読むでしょうか?関西人であれば、この文字列を読むとなると無意識に「かんさい~でんきほ~あんきょ~かい♪」とリズミカルに歌ってしまいがちなのです。これは関西のテレビCMとして流れている関西電気保安協会のCMの影響。テレビCMとして長年にわたって刷り込まれた結果、自然と歌ってしまうのですね。
出展:関西電気保安協会
最後に
今回は関西人しか読めない文章や関西人じゃないとうまく読めない早口言葉などについて紹介しました。独特なイントネーションの言葉が多い関西弁ですが、関西弁を話す芸人なども全国区で多く活躍しているため、近年は関西弁に馴染んでいる人も全国に多いです。関西でしか通じない言葉というのは、これからもどんどん減っていくのかもしれませんね。